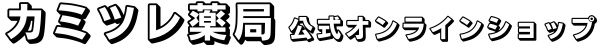- ホーム
- 「気虚(ききょ)」とは?原因・症状・改善法を解説|おすすめ漢方薬と食事のポイント
気虚(ききょ)とは?
漢方では、カラダは「気(き)」・「血(けつ)」・「水(すい)」の3つの構成要素で支えられていると考えます。
「気」とは目には見えない「生命エネルギー」「精神エネルギー」のことで、「気」が不足してエネルギーが足りていない状態を「気虚(ききょ)」といいます。
(※ 「気滞(きたい)」は、「気」の巡りが悪くなり、気が滞っている状態です。)
「気」は、「飲食物を消化器系で消化吸収すること」または、「呼吸で肺に酸素を取り入れること」によって生成されると考えられます。
そのため、漢方医学では「気虚」になると、疲れ、だるさをはじめとする、さまざまな症状があらわれます。
「気虚」を現代的な言葉で簡単に説明すると「各臓器や器官などの機能低下」とも言えるでしょう。
気虚の症状1:疲れやすく、元気がでない
生命エネルギーである「気」が不足して「気虚」になると、運動機能の低下や慢性的な疲労感を感じ、元気を出したくても出せなくなってしまいます。
また、疲れやすく、元気がないといった症状のため、無意識に座ったり横になったりする頻度が増え、日中でも眠気を感じやすくなります。また、口数が減り、声も小さくなりがちです。
気虚の症状2:風邪をひきやすい、感染症にかかりやすい
生命エネルギーである「気」が不足して「気虚」になると、抵抗力(免疫力)が落ちることで外部からのウイルスや細菌に対する影響を受けやすく、風邪やインフルエンザなどの感染症や、花粉、ハウスダストなどのアレルギー症状にもかかりやすくなります。
気虚の症状3:気分が落ち込み、やる気がでない
生命エネルギーである「気」が不足して「気虚」になると、気力の低下により気分が落ち込みやすくなってしまったり、やる気がなかなか出なくなり、無気力になり、鬱(うつ)状態にもなりやすくなります。
気虚の症状4:食欲がない、消化が悪い、食後の眠気
生命エネルギーである「気」が不足して「気虚」になると、胃腸の機能が低下し食欲不振や、消化吸収機能の低下、消化不良などによって下痢軟便傾向になります。また、臓器の弛緩による内臓下垂や脱肛など様々な症状が起こりやすくなります。
気虚の症状5:手足やカラダが冷える
生命エネルギーである「気」が不足して「気虚」になると、新陳代謝の低下などにより体を温める力も弱まり、体の冷えにつながります。
そそのため、冷たいものを嫌い、温かいものを欲しやすく、手足の冷えを感じ、低体温にもなりやすくなります。
「気虚」に使用される代表的な漢方薬
気虚の改善に使用される漢方薬は、「気(き)」の不足を補う「補気剤」と呼ばれる漢方です。
- 四君子湯(しくんしとう)
- 六君子湯(りっくんしとう)
※ 四君子湯と二陳湯を合わせた処方 - 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
- 人参養栄湯(にんじんようえいとう)
- 人参湯(にんじんとう)
- 帰脾湯(きひとう)
- 玉屏風散(ぎょくへいふうさん)
- 清暑益気湯(せいしょえっきとう)
- 清心蓮子飲(せいしんれんしいん)
- 補気建中湯(ほきけんちゅうとう)
- 安中散(あんちゅうさん)
「気虚」の方が注意する飲食物
気虚の人は基本的には「胃腸が弱っている」ことが多いので、胃に負担をかけるものを避けることが大事です。次の飲食物は避けましょう。
- 冷たい飲み物、食べ物
- 生もの(刺身や生野菜)
- 脂っこいもの(脂質)
- 甘いもの(チョコレートなど)
- 刺激の強いもの(唐辛子など)
「気虚」の方におすすめの飲食物
気虚の人は基本的には「胃腸が弱っている」ことが多いので、胃に負担をかけるものを避けることが大事です。次の飲食物を積極的にとりましょう。
- 胃腸が弱く食欲不振で下痢や軟便の多い人
イモ類(長芋、山芋など)、豆類など - 元気がない、倦怠感の強い人
牛肉、鶏肉、エビ、ウナギ、薬用人参 - 感染症にかかりやすい人
キノコ類、ブロッコリー、アスパラガスなど - 手足など末端に冷えを感じる人
ニンニク、ショウガ、ネギ、玉ねぎ、ニラ、サンショウ、シナモンなどの香味野菜