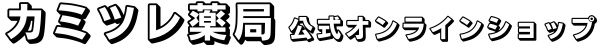- ホーム
- 「気滞(きたい)」とは?原因・症状・改善法を解説|おすすめ漢方薬と食事のポイント
気滞(きたい)とは?
漢方では、カラダは「気(き)」・「血(けつ)」・「水(すい)」の3つの構成要素で支えられていると考えます。
「気」とは目には見えない「生命エネルギー」「精神エネルギー」のことで、「気」の巡りが悪くなり、気が滞っている状態を「気滞(きたい)」といいます。
(※ 「気虚(ききょ)」は、「気」が不足している病態です。)
「気」は、「飲食物を消化器系で消化吸収すること」または、「呼吸で肺に酸素を取り入れること」によって生成されると考えられます。
そのため、漢方医学では「気滞」になると、臓器の機能異常や精神的なストレスによる異常など、さまざまな症状があらわれます。
「気滞」を現代的な言葉で簡単に説明すると「機能異常」とも言えるでしょう。
気の停滞(気滞)による「自律神経の異常」が原因となり次のような症状が起こるといわれています。
気滞の症状1:精神不安、イライラなど
生命エネルギーである「気」の巡りが悪くなり「気滞」になると、精神が不安定になり、イライラしやすい、怒りやすい、気持ちの浮き沈みが激しい、憂鬱になるなどの精神不安症状があらわれます。
また、緊張しやすい、些細なことが気になる、神経質など神経症の症状が出やすくなるとも言われています。
漢方では、精神ストレスによる気滞の病態は「肝鬱(かんうつ)」「気鬱(きうつ)」「肝鬱気滞(かんうつきたい)」などとも呼ばれ、中でも症状がより重いケースである「肝気鬱結(かんきうつけつ)」は、憂うつ感、イライラ、頭痛、のぼせ、月経異常などの不調があらわれます。
そのため、気の巡りが良く安定している状態にすることで、精神も安定し穏やかになります。
気滞の症状2:ノドに何か詰まったような違和感
生命エネルギーである「気」の巡りが悪くなり「気滞」になると、喉がつかえるような違和感、異物感を感じることがあります。
漢方では梅の種がのどに詰まった感覚と似ていることから「梅核気(ばいかくき)」とも呼ばれています。
気滞の症状3:胸・みぞおち部分が張って苦しい
生命エネルギーである「気」の巡りが悪くなり「気滞」になると、体の空洞に余分な気が溜まりやすくなります。そのため、体の空洞である胸やみぞおちが張ったように苦しくなったり、下着などでしめつけられるのが苦痛に感じたり、時には痛みを感じやすくなると考えられています。
ストレスなど精神不安によって症状が悪化することが多く、逆にリラックスやため息などで症状が軽減するのも気滞の症状の特徴といわれています。
気滞の症状4:お腹が張る、ゲップやオナラなどが多い
生命エネルギーである「気」の巡りが悪くなり「気滞」になると、胃腸などの空洞に余分な気が溜まり、胃の張りや膨満感、お腹の張りや痛み、ゲップやおならが多いなどの症状が出やすくなると言われています。
また胃腸の機能異常により胃酸の逆流、吐き気、嘔吐、下痢や便秘を繰り返すなどの症状があらわれます。
気滞の症状5:生理周期の異常、生理前に胸が張る
生命エネルギーである「気」の巡りが悪くなり「気滞」になると、生理にも大きな影響を与えます。
気滞になると生理周期が安定せず、バラつきやすくなると考えられ、生理前に胸が張る、イライラしやすくなる、精神的に不安定になる、食欲が乱れるなどの症状も出やすくなると言われています。また、気滞が原因の生理痛はお腹の張ったような痛みなのが特徴で、ストレスにより悪化しやすいと言われています。
月経前緊張症や月経前症候群(PMS)とも呼ばれる症状も、漢方では気滞が原因と考えられています。
「気滞」に使用される代表的な漢方薬
気虚の改善に使用される漢方薬は、「気(き)」の不足を補う「理気剤」と呼ばれる漢方です。精神症状を中心とした「肝気鬱結(かんきうつけつ)」を改善する場合には、柴胡(さいこ)という生薬を処方の柱とする「疏肝理気剤(そかんりきざい)」と呼ばれるものもあります。
- 加味逍遙散(かみしょうようさん)
- 甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)
- 柴胡疎肝湯(さいこそかんとう)
- 柴胡加竜骨牡蠣湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)
- 柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)
- 柴朴湯(さいぼくとう)
- 四逆散(しぎゃくさん)
- 小柴胡湯(しょうさいことう)
- 小柴胡湯加桔梗石膏(しょうさいことうかききょうせっこう)
- 逍遙散(しょうようさん)
- 釣藤散(ちょうとうさん)
- 女神散(にょしんさん)
- 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
- 抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)
「気滞」の方におすすめの飲食物
気滞の人は、次の飲食物を積極的にとるとよいと言われています。
- 片頭痛や月経不順、PMSに悩む人(肝気鬱結タイプ)
ミツバ、シュンギク、セリ、セロリ、パセリなどの香味野菜(香りが強い野菜ならOK)、柑橘類 - 怒りっぽい、イライラが止まらない、憂うつ感や不安感が強い人
酸味の強い柑橘類(レモン、ミカン、スダチ、オレンジなど)、酢を使った料理 - 肝機能に失調があったり、眼精疲労などの目のトラブル、筋肉痛や痙攣のある人
レバー、しじみ、アサリ、クコの実、菊花、ブルーベリーなど - 不眠がちな人
ミント、ラベンダー、ジャスミン、カモミールなど鎮静作用のあるハーブ類