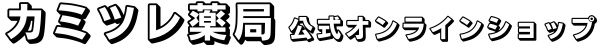- ホーム
- 熱証(ねっしょう)とは?ほてりやイライラの原因、タイプ別の症状と改善法を解説
熱証(ねっしょう)とは?
「熱証」とは、体に熱がこもっている状態を指します。
東洋医学では、病気の原因となるものを「病邪(びょうじゃ)」と呼び、その中でも熱によって引き起こされるものを「熱邪(ねつじゃ)」といいます。
この熱邪が体内に侵入することで、さまざまな不調が引き起こされます。
また、「熱証」は「実熱証」と「虚熱証」に分けられます。
実熱証(じつねつしょう)
「実熱証」は、熱邪が体に停滞したもので、体表で起こるもの(表証)と体内で起こるもの(裏証)があります。
暑い日などには熱邪が体表(表証)に停滞すると、急性の症状が多く、発熱、頭痛、喉の痛み、黄色い鼻水などの症状がみられます。
また、体内(裏証)の場合は、慢性の症状が多く、辛い物や脂っこい物の摂りすぎなどで腹痛や胸やけ、胃もたれ、便秘、肛門部の灼熱感を訴えるなど、熱邪が胃腸に停滞している状態といえます。
虚熱証(きょねつしょう)
「虚熱証」は、体内の潤い(津液)が不足したことで、陽気が増大して熱感がでる状態で「陰虚」と呼ばれることもあります。
顔や手足のほてり、のぼせ、乾燥肌、尿量の減少、口の渇き、便秘などの症状が特徴です。
「熱証」の症状1:顔色が「赤い」か「黄色い」
「熱証」は顔色が赤く、あるいは黄色で、「寒証」は顔色が白いかどす黒いとされています。
「熱証」の症状2:発熱がする
熱感が悪寒より強ければ「熱証(表熱)」、悪寒が強ければ「寒証(表寒)」とされます。
「熱証」の症状3:口が乾く、冷たいものを飲みたがる
口渇が強い場合は「熱証」と判断します。
冬でも冷たい飲み物の方が好きだというのは「熱証」、夏でも温かい飲み物を好むというのは「寒証」とされます。
「熱証」の症状4:暖房が苦手
冷房はどうしても苦手という人は「寒証」で、暖房はのぼせて気分が悪くなるから苦手という人は「熱証」とされます。
「熱証」に使用される代表的な漢方薬
「実熱証」の改善には「清熱(せいねつ)」すなわち「熱を冷ますこと」です。
そのため、熱を冷ます「清熱剤(せいねつざい)」と呼ばれる漢方薬が使用されます。
※ 下記は「実寒証(体内・体表)」に用いる漢方薬です。「虚熱証」に用いる漢方薬は「陰虚」を参照。
- 温清飲(うんせいいん)
- 黄連解毒湯(おうれんげどくとう)
- 乙字湯(おつじとう)
- 桔梗石膏(ききょうせっこう)
- 荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)
- 五虎湯(ごことう)
- 五淋散(ごりんさん)
- 柴胡清肝湯(さいこせいかんとう)
- 三物黄芩湯(さんもつおうごんとう)
- 消風散(しょうふうさん)
- 十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)
- 清上防風湯(せいじょうぼうふうとう)
- 竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)
- 白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)
「熱証」の方におすすめの飲食物
熱証の人は、カラダの熱を鎮める作用のある寒性・涼性の食べ物を、カラダを冷ましすぎない程度にとるよう心がけましょう。
辛い食べ物や刺激物の摂取は、熱証を悪化させるので避けましょう。
- 寒性・涼性の食べ物
キュウリ、トマト、ゴボウ、セロリ、大根、冬瓜、白菜、ゴーヤ、アサリ、牡蠣、ハマグリ、カニ、スイカ、梨、ウーロン茶、緑茶 など
また、熱いお風呂や激しい運動は控え、ぬるま湯にサッと浸かったり、軽く汗をかく程度の運動を心がけることも重要です。
カラダの熱を冷ますためには、体の内部の熱がこもらないように適度に発散させることも大切です。