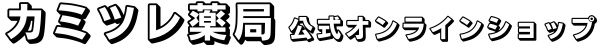- ホーム
- 「水滞(すいたい)」とは?原因・症状・改善法を解説|おすすめ漢方薬と食事のポイント
水滞(すいたい)とは?
漢方では、カラダは「気(き)」・「血(けつ)」・「水(すい)」の3つの構成要素で支えられていると考えます。
「水」は体のすべての水分の総称で、体液だけでなく、汗や唾液、胃液、腸液、尿のような分泌液や排泄液なども入ります。
「水」はカラダを潤す役割とともに、カラダにたまった不要な老廃物を尿や汗、鼻水などと共に体外へ排出する役割も担っています。
「水滞(すいたい)」は「水毒(すいどく)」ともいわれ、体液(津液:しんえき)の流れが停滞している病態のことを言います。
水滞が長期化すると「痰湿(たんしつ)」「痰飲(たんいん)」というさらに体に害を及ぼす状態となります。
人間の体の6〜7割は水分といわれるため、「水滞」は、水の巡りが悪くなるだけでなく、余分な水や老廃物がカラダのあらゆるところに溜まりやすくなるため、さまざまなトラブルが起こりやすくなります。
水滞の症状1:浮腫(むくみ)
水滞になり余分な水がカラダに停滞すると、全身が「むくみ」やすくなると考えられます。
特に、ふくらはぎや足首など下半身はむくみやすい部位で、ひどいときにはだるさや痛みを伴うこともあります。関節も余分な水がたまってむくみやすい部位で、指が曲げにくい、こぶしが握りにくい、腕が上がりにくい、動かしにくいなどのトラブルが出やすいと言われています。
水滞の症状2:体の重だるさ、頭重感
水滞になり余分な水がカラダに停滞すると、カラダが重く、重だるい、動きにくいなどと感じやすくなると考えられます。
また、頭痛も起こりやすく、その特徴は「頭の上に重い石を乗せたような痛み」の頭重感や、「きつい帽子をかぶって締め付けられるような痛み」の頭帽感として表現されます。
雨や台風など天気が悪くなると頭痛が悪化しやすいのも水滞の頭痛の特徴です。
水滞の症状3:眩暈(めまい)
水滞になり余分な水が「耳」に停滞すると、それが原因でめまいを起こしやすくなると考えられます。
水滞によるめまいは、「ふわふわする(浮動感)ようなめまい」や、「グルグル回るような回転性のめまい」が特徴で、これは西洋医学のメニエール病(内リンパ水腫・内耳のむくみ)に相当すると考えられています。
水滞の症状4:胃腸の不調
水滞になると胃腸の不調が起こりやすいといわれています。
漢方では、食べ物の消化吸収を担っている「脾(胃腸などの消化器系)」は湿を嫌い、燥を好むと言われていますが、水滞体質は脾に余分な水が溜まりやすく、不調を起こしやすくなると考えられているため、水滞になると悪心や嘔吐、腹部の膨満感、食欲不振、下痢や軟便などのさまざまな胃腸トラブルが起こりやすいと言われます。
水滞の症状5:天気が悪くなると体調悪化
水滞体質は水分の侵入にとても敏感で、天気が悪くなるとカラダが重だるくなることが多く、台風が近づくと頭痛やめまいがするといった症状が起こります。
また、お風呂など湿気の多い場所に入ると気分が悪くなる、水を多く飲むと体調が悪くなるなど、カラダに余分な湿気や水が入ってくるような環境になると症状が出たり、悪化するといった傾向が見られます。
「水滞」に使用される代表的な漢方薬
水滞の改善に使用される漢方薬を「利水剤(りすいざい)」と呼ばれ、体液(津液)の流れを正常化し、余分な水や老廃物の排出をすることで水滞の症状を改善します。
- 五苓散(ごれいさん)
- 柴苓湯(さいれいとう)
- 茵陳五苓散(いんちんごれいさん)
- 藿香正気散(かっこうしょうきさん)
- 沢瀉湯(たくしゃとう)
- 猪苓湯(ちょれいとう)
- 二陳湯(にちんとう)
- 防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)
- 苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)
- 加味平胃散(かみへいいさん)
「水滞」の方におすすめの飲食物
水滞が起こる主な原因としては、過剰な水分摂取や胃腸機能の低下、湿気の強い生活環境などがあります。
また、砂糖を大量に含む食べ物やフルーツも体に湿邪をため込む原因になるので、食べすぎには注意が必要です。
水滞の人は、特に次のような飲食物を積極的にとるよう心がけましょう。
- 豆類(小豆、大豆、枝豆、黒豆、そら豆など)
- ハトムギ、トウモロコシ、ナス、トウガン、シソ、ショウガ、緑豆もやし など