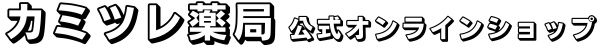- ホーム
- 「同病異治」と「異病同治」の考えについて
「同病異治」と「異病同治」とは
頭痛に効く漢方薬は一つではない?まったく違う症状なのに、同じ漢方薬が使われるのはなぜ?
漢方薬(漢方医学)には、西洋医学とは異なる独自の考え方「同病異治(どうびょういち)」と「異病同治(いびょうどうち)」があります。
この記事では、この2つの概念を分かりやすく解説します。
同病異治(どうびょういち)とは
『同病異治』とは、同じ病気でも体質が違えば、人によって異なる治療をするということです。
そのため、頭痛の症状では西洋医学ではロキソプロフェンやアセトアミノフェンなどの鎮痛薬が処方され基本的には同じ治療をしますが、漢方薬では「葛根湯」や「五苓散」「釣藤散」「半夏白朮天麻湯」など多くの漢方薬が使用されます。
漢方医学では、体格や睡眠状態や消化器系の弱り、睡眠状態など体質(証)を考慮し、同じ「頭痛」という症状に対しても、人によってさまざまなアプローチをするというものです。
例えば、同じ頭痛でも、肩こりが原因で起こる頭痛には『葛根湯』、起床時やイライラした時に頭痛を感じたり、血圧が高くなる人には『釣藤散』、胃腸が弱っていて足の冷えがある方の頭痛には『半夏白朮天麻湯』など、その人の体質や状態(証)を考慮して処方する漢方薬は変わってきます。
異病同治(いびょうどうち)
『異病同治」とは、異なる病気や症状に対して、同じ治療を行うということです。
最も有名な漢方薬の一つである『葛根湯』では、「風邪」の症状で使用されることが多いですが、「肩こり」や「湿疹」「中耳炎」「扁桃腺炎」「筋肉痛」など多くの病気や症状に使用することがあります。
これは、漢方医学がその人の体質や症状を診るため、西洋医学でいう病名が違っていたとしても改善したい症状や体質(証)が共通している場合には、同じ漢方薬を用いて治療を行うことを示しています。
まとめ
-
同病異治: 同じ病気(例:頭痛)でも、体質や原因が違う場合は異なる漢方薬を使う。
-
異病同治: 異なる病気(例:風邪と肩こり)でも、体質や症状に共通点があれば同じ漢方薬を使う。
-
漢方薬は、病名だけでなく、一人ひとりの体質や症状を総合的に診て選ぶことが重要です。