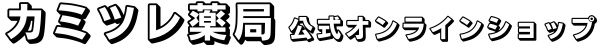- ホーム
- 寒証(かんしょう)とは?冷え性との違い、タイプ別の原因・症状・改善法を解説
寒証(かんしょう)とは?
「寒証」とは、体に冷えが溜まっている状態を指します。(「寒」:冷えのこと)
東洋医学では、病気の原因となるものを「病邪(びょうじゃ)」と呼び、その中でも冷えによって引き起こされるものを「寒邪(かんじゃ)」といいます。
この寒邪が体内に侵入することで、さまざまな不調が引き起こされます。
また、「寒証」は「実寒証」と「虚寒証」に分けられます。
実寒証(じつかんしょう)
「実寒証」は、寒邪が体に停滞したものですが、体表で起こるもの(表証)と体内で起こるもの(裏証)があります。
寒い日などには寒邪が体表(表証)に停滞すると、急性の症状が多く悪寒や震え、頭痛、サラサラした鼻水などの症状がみられます。
また、体内(裏証)の場合は、慢性の症状が多く、冷たいも飲食物の摂りすぎなどで腹痛や下痢を訴えるなど、寒邪が胃に停滞している状態といえます。
虚寒証(きょかんしょう)
「虚寒証」は、体内の陽気が消耗した状態で「陽虚」と呼ばれることもあります。
手足の冷え、寒がり、尿や汗、鼻水がサラサラした透明な状態になるというのが症状の特徴です。
「寒証」の症状1:顔色がくすむ(白い・どす黒い)
「熱証」は顔色が赤い、あるいは黄色で、「寒証」は顔色が白いかどす黒いとされています。
「寒証」の症状2:寒気(悪寒)がする
熱感が悪寒より強ければ「熱証(表熱)」、悪寒が強ければ「寒証(表寒)」とされます。
「寒証」の症状3:口が乾かない、熱いものを飲みたがる
口渇が強い場合は「熱証」と判断しますが、口渇がなかったり、少しはあるといった程度であれば熱証とも寒証とも言えないとされます。
冬でも冷たい飲み物の方が好きだというのは「熱証」、夏でも温かい飲み物を好むというのは「寒証」とされます。
「寒証」の症状4:暑い夏でも冷房が苦手
冷房はどうしても苦手という人は「寒証」で、暖房はのぼせて気分が悪くなるから苦手という人は「熱証」とされます。
「寒証」に使用される代表的な漢方薬
「寒証」の改善には「補陽散寒(ほようさんかん)」すなわち「温めること」です。
そのため、カラダを温める「祛寒剤(きょかんざい)」と呼ばれる漢方薬が使用されます。
※ どの漢方薬を「実寒証(体内・体表)」「虚寒証」に用いるかは個別のケースによります。
- 当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)
- 真武湯(しんぶとう)
- 桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう)
- 桂枝芍薬知母湯(けいししゃくやくちもとう)
- 大建中湯(だいけんちゅうとう)
- 五積散(ごしゃくさん)
- 呉茱萸湯(ごしゅゆとう)
- 蘇子降気湯(そしこうきとう)
「寒証」の方におすすめの飲食物
外寒、内寒ともにカラダを温めて冷やさないことが重要です。特に、内寒は冷たいものの過剰摂取を避けることが必要です。
寒証の人は、特に次のような飲食物を積極的にとるよう心がけましょう。
- 外寒(寒邪の体表部への侵入)
ミツバ、大根、生姜、ネギ、白菜、クズ、ヨモギなど内臓を温め寒邪を除去する食材 - 内寒(体内の陽気不足や寒邪の侵入)
シナモン、生姜、ネギ、黒砂糖、鶏肉、黒ゴマ、ラッキョウなど体を温め陽気を補う食材